七福神とは
- もともと中国の「七難即滅 七福即生」という仏教語に由来したもの。
- 日本では「福徳の神」として信仰される七柱の神を意味する。
- 神様は1人(ひとり)、2人(ふたり)とは数えず、1柱(ひとはしら)、2柱(ふたはしら)と数える。
- なぜ「七」なのか?
- 七福神の信仰は、仏教経典の「七難即滅七福即生しちなんそくめつしちふくそくしょう」から生まれた。
- 七つの難(天変地異や病気、恨みや盗難など)がたちまち消滅し、
- 七つの幸福(長寿、子宝、幸運、人望、知恵など)がもたらされるという意味。
- 七福神の信仰は、仏教経典の「七難即滅七福即生しちなんそくめつしちふくそくしょう」から生まれた。
- 鎌倉~室町時代の頃に、幸福を呼ぶ神様として庶民に信仰され今に至る。
- 七福神すべてが幸福を与えてくれるので、満面の笑みを浮かべている。
ご真言とは
- ご真言は、マントラ(サンスクリット語)のことを指し「仏の真実の言葉、秘密の言葉」という意味。
- 教経典に由来し、浄土真宗を除く多くの大乗仏教の宗派で用いられる呪術的な語句。
- 仏の言葉を音写したもので、真言を唱えることで効果を享受することができる。
七福神とご真言
一:弁財天[べんざいてん]
弁財天とは
水の神様
弁財天は七福神の中で唯一の女性の神様であり、もともとはインドのヒンドゥー教の女神であった。後に仏教に取り入れられ、音楽、弁才、財福、知恵の徳を持つ神様。

ご真言/マントラ
おん・そらそばていえい・そわか
特徴
七福神で唯一の女性の神様で、琵琶を持っている。
ご利益
財運・芸能・芸術・音楽
弁財天が祀られている神社
二:大黒天[だいこくてん]
大黒天とは
五穀豊穣の神様
大国天はインドのヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラ神であった。日本では、日本神話に出てくる大国主神として習合される。
大国天は食物や財福を司る神として崇拝されており、「大黒柱」として表現される。また、親子関係に関連して恵比寿(子)と一緒に描かれることもよくある。


ご真言/マントラ
おん・まかきゃらや・そわか
特徴
右手に打出の小槌、左手に福袋を背負っている。
ご利益
商売繁盛・五穀豊穣・財運福徳
大黒天が祀られている神社
三:恵比寿天[えびすてん]
恵比寿とは
農業・漁業の神様
恵比寿天は、伊邪那岐命と伊邪那美命の間に生まれた子供である「蛭子」や、大国主神の息子である「事代主神」などを祀ったものであり、七福神の中で唯一の日本の神様である。漁業の神として「大漁追福」として崇拝され、時代とともに福の神として、商売繁盛や五穀豊穣をもたらす神とされた。


ご真言/マントラ
おん・いんだらや・そわか
特徴
片手には釣り竿、わきに鯛を挟んでいる。
ご利益
商売繁盛・庶民救済
恵比寿天が祀られている神社
四:寿老人[じゅろうじん]
寿老人とは
長寿の神様
寿老人は、道教の神仙であり、中国の伝説上の人物。
南極老人星(カノープス)の化身とされる。お酒が大好きで長寿の神とされている。
福禄寿と同一の神様とされることもあり何ともややこしい。


ご真言/マントラ
おん・ばざら・ゆせい・そわか
(うん・ぬん・しき・そわか)
特徴
髭は福禄寿程長くはない。
杖を持ち鹿を連れている。
手に桃を持っていることが多い。
ご利益
長寿延命・家庭円満
寿老人が祀られている神社
五:毘沙門天[びしゃもんてん]
毘沙門天とは
戦勝の神様
毘沙門天は、元々はインドのヒンドゥー教の神であり、別名「ヴァイシュラヴァナ」とも呼ばれ、日本ではヴァイシュラヴァナの語源から毘沙門天と呼ばれるようになった。
戦いの神として民衆に信仰される。ヴァイシュラヴァナは「多くのことを聞き、言葉を逃さずに聴く者を意味する。」という意味があり、四天王の一人「多聞天たもんてん」としても称されている。


ご真言/マントラ
おん・べいしらまんだや・そわか
特徴
インド出身の神様。甲冑を身につけ、武将のような身なりをしている。
ご利益
財運・武道成就・七難即滅
毘沙門天が祀られている神社
六:布袋尊[ほていそん]
布袋尊とは
商売繁盛の神様
布袋尊は、唐代末から五代時代に実在したと言われる伝説的な仏僧。布袋尊が持っている袋は「喜捨物」を入れる袋であり、堪忍袋とも呼ばれ、この袋には喜捨(気前よく施しをすること)することで、人格を円満に導く功徳があるとされている。袋を背負っていたことから「布袋」と呼ばれるようになった。
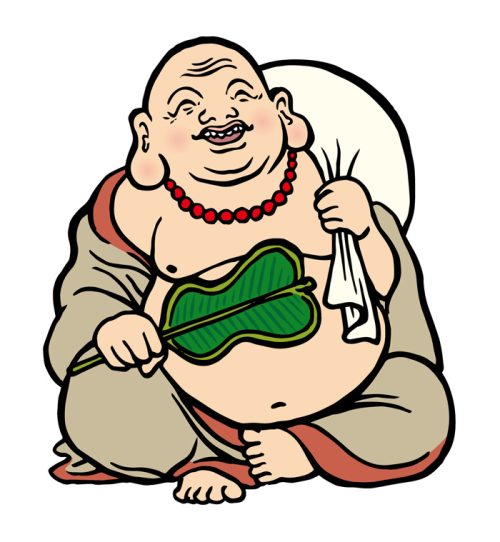
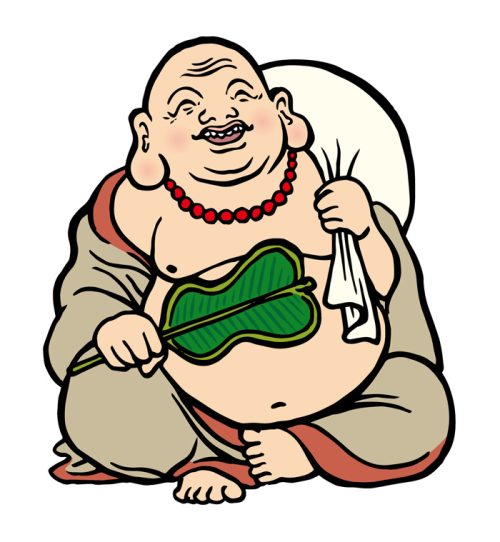
ご真言/マントラ
おん・まいたれいや・そわか
特徴
中国に実在した人物。太っておおらかな風貌であり、大きな袋と軍配を持っている。
ご利益
夫婦円満・笑門来福・千客万来・商売繁盛
布袋尊が祀られている神社
七:福禄寿[ふくろくじゅ]
福禄寿とは
幸福、富、長寿の神様
福禄寿は道教の神であり、南極星(カノープス)の化身である南極老人である。道教において非常に重要視される3つの願い、福(血のつながった実の子に恵まれること)、禄(財産)、寿(健康を伴う長寿)を具現化した存在とされる。長い頭は知恵者の象徴でもある。


ご真言/マントラ
おん・まかしり・そわか
(うん・ぬん・しき・そわか)
特徴
長~い頭と長~い耳たぶ、長~い髭で、仙人のような顔立ち。左手に巻物、右手に杖を持っている。
ご利益
子宝・財運招福・健康長寿
福禄寿が祀られている神社
ご真言のご利益と効果のまとめ
「ご真言」とは、マントラ(サンスクリット語)のことを指し「仏の真実の言葉、秘密の言葉」という意味がある。
七福神にご真言があるように、他にもたくさんのご真言が存在する。
それぞれまとめているので、是非お気に入りのご真言を見つけてみてほしい。












